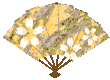薄闇の中、自分の胸元へ甘えたように擦り寄ってきたセピアの髪に
零一はそっと口付けた。さっきまで腕枕の中で大人しく寝息を立てて
いたと思ったら、不意にごそごそと頭の位置が零一の顎の辺りから
下がってきたのだ。伸ばした腕も既に枕の役割を果たせなくなったのだが、
腕を動かすことも億劫なので伸ばしたまま放置しておく。
裸の胸にかかる秋の吐息が擽ったくて身を捩って姿勢を変えようとしたら。
「感じた?」
悪戯っぽくきらめく瞳と目が合った。一体いつから起きていたのだろうか。
「馬鹿、くすぐったいに決まってんだろ」
「それって感じてるんだよー?」
クスクスと零一の胸に顔を寄せて笑う子悪魔を何とか黙らせようと、
彼は秋の顔を半ば強引に上げさせてキスをした。唇を割って舌を侵入
させても秋は抵抗らしい抵抗を見せず、細い指を零一の頬に這わせて
甘噛みをする。時折離れる唇から、くちゅりと粘着質な音が響いた。
「……ん、リン…っ」
二人きりの時だけ使われる呼び名を聞いて、零一はようやく秋を
解放した。零一が、受け止め切れずに滴ったどちらのものともつかぬ
唾液を秋の口元から舐め取り、額が触れ合うほどの至近距離で囁く。
「いっつもそんなしおらしかったら可愛いのにな、お前」
秋は意外にもキスに弱い。こういうことに関して零一が優勢に立てる
ことなど絶対ないだろうと、彼は自分でそう思っていたから、秋の
弱点を発見したときの喜びは筆舌に尽くしがたいほどのものだった。
「オトコノコに言う台詞じゃないよ、それ」
「女にもなれるくせに」
「なって欲しい?」
「いや、今のままが良い」
楽しそうに笑う秋の首筋に顔を埋めて、しるしを一つ落とす。
きつく吸うと秋の体はぴくりと痙攣して、おもしろいように反応を
返してくる。
「ね、リン?」
「何だよ」
顔を上げずに聞き返したら、秋の体がずるずると下方に移動して
零一と目が合う位置に頭を持ってきた。日焼けとは縁遠い白い肌が、
月明かりの下で透けそうなほどに儚く見えて。零一はその冷たい頬を
自分の無骨な手で包んだ。
「僕のこと、どれくらい好き?」
あくまで口調は可愛らしく言ったつもりなのだろうが、目が全てを
物語っていた。期待と不安、怯え。いつも誘ってくるのは秋の方からで、
言葉を発するのも秋がいつも先手を切っているから、不安に
苛まれるのだ。零一の心は、異種族の彼にとって把握し切れない
部分なのだろう。
率直に言って、零一の中で秋はかなり大きい存在になっている。
それは勿論零一自身も気付いていることだ。自分が秋に対して
何かしらの感情を抱いていることも気付いている。だが、
それは<好き>や<愛している>といった睦言に相当するも
のなのだろうか。どちらも相応しい気がするし、どちらも不適当な
気もする。だから零一は秋に対してそういった台詞を言ったことがない。
だが、それが秋を不安にさせている要素に他ならないのだろう。
「……嫌いだったら、とうに見捨ててる」
「答えになってないよ?」
切り抜けたつもりだったが、秋は零一の返答にご不満な点があるらしい。
「次逢う時までに答え考えといてね。400字詰め原稿用紙五枚に反省文付きで」
「俺が何の反省するんだよ」
「さっき、即答してくれなかったじゃん」
拗ねたような口調に苦笑して、零一は不満そうな秋の唇を親指でなぞった。
先ほどの口付けで潤ったそこは冷えていて、陶器の人形を思い出させた。
どこか頼りなげな、子どものような表情に零一の庇護欲が掻き立てられる。
「……幸せにするから、絶対」
零一の口をついて出た言葉に、秋が嬉しそうに微笑む。
あの時と同じ台詞、同じ笑顔。
「ありがと。大好きだよ、リン」
既視感に捕らわれて、零一の思考が一瞬停止する。自分が同じように
約束し、彼も同じように微笑んで答えたあの日。
あの時の自分の一言を信じて、秋はずっと自分に付いてきたのだ。
零一は誓うように、秋の唇へそっと自分のそれを重ねる。
深く合わせずに、羽毛が触れるようなキスはどこか神聖過ぎる気がして、
零一は唇を離してそっと苦笑した。
悪魔である自分には相応しくない、清廉過ぎるこの思い。
たとえ行き付く先が破滅であろうとも、零一には秋を手放す
ことなどできないだろう。
やがて胸元で安らかな寝息を立て始めた秋を見て、
零一は心のどこかが軋む音を聞いた気がした。